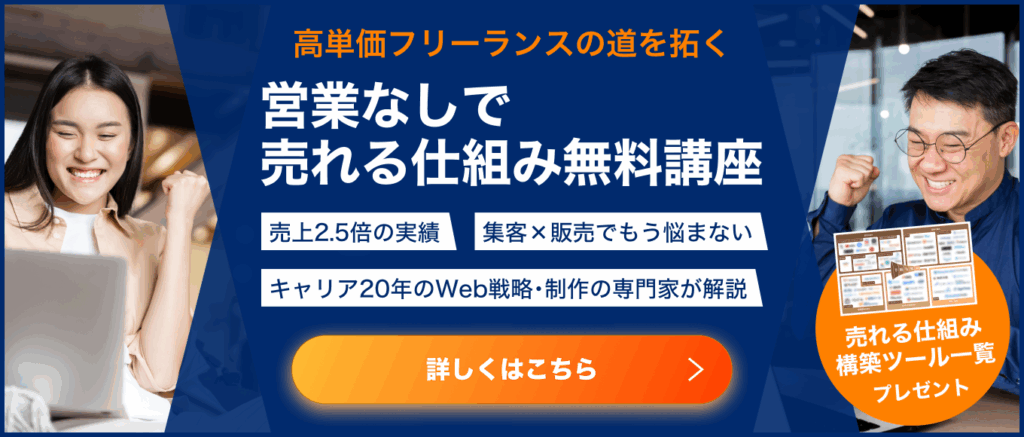


この記事では、売れる文章を書くための基礎知識から、LPやブログなど目的別に使える代表的な型、すぐに実践できるコツまでを網羅的に解説します。
初心者の方でも、この記事の手順に沿って書くだけで、読者の心を動かし行動を促す文章が作れるようになります。
セールスライティングに役立つ心理学や書籍も併せてご紹介していますので、ぜひ最後までご確認ください。

まずは、セールスライティングがどのようなものか、基本的な知識から解説します。
売れる文章を書くための土台となる部分ですので、しっかり押さえていきましょう。
セールスライティングとは、その名の通り「セールス(販売)」を目的とした文章術のことです。
文章の力で読み手の感情を動かし、商品購入やサービスへの申し込み、問い合わせといった具体的な行動を促します。
ただ単に商品の特徴を説明するだけでなく、読み手が抱える悩みや欲求に寄り添い、「これが私のための商品だ」と感じてもらうことが重要です。
そのため、心理学に基づいたテクニックが用いられることも多く、Web広告やランディングページ(LP)など、売上に直結する多くの場面で活用されています。
セールスライティングの最終的な目的は、文章を通じて「読み手を行動させ、売上を最大化する」ことです。
見込み客が抱える商品への不安や疑問を取り除き、購入への最後のひと押しをします。
この目的を達成するため、セールスライティングでは商品の特徴(Feature)だけでなく、それによって顧客が得られる未来や価値(Benefit)を具体的に描き出すことが求められます。
セールスライティングと混同されやすい言葉に「コピーライティング」と「コンテンツライティング」があります。
それぞれの目的には違いがあり、シーンによって使い分けられます。
ただし、これらの境界は曖昧な場合もあります。
例えば、コンテンツライティングの記事内でセールスライティングの要素を取り入れ、商品の購入につなげることもあります。
目的に応じて、それぞれの良い部分を使い分けることが大切です。
大切なのは「今、この記事で、誰に・どうなってほしいのか?」という目的意識です。
その目的を達成するために、セールス、コピー、コンテンツの要素を柔軟に組み合わせるのが実践的です。
セールスライティングは、読み手に行動を促したいあらゆる場面で活躍します。
特にWebマーケティングでは欠かせないスキルです。
このように、オンライン・オフラインを問わず、売上が発生する場所には必ずと言っていいほどセールスライティングの技術が活かされています。

売れる文章は、思いつきでは書けません。
ここでは、セールスライティングを実践するための基本的な5つのステップをご紹介します。
この5ステップ、特に最初の3ステップ(調査・分析)は地味に見えますが、実は文章を書くための心臓部です。
ここを飛ばして書き始めると、途中で「この記事、誰のためにどんな視点で書くんだっけ…?」と迷子になりがちです。
まず、アピールしたい自社の製品・サービスについて、その特徴や強み、提供できる価値などを客観的に洗い出します。
この段階で、製品・サービスが持つあらゆる価値の可能性を洗い出しておくことが、後のステップで説得力のあるメッセージを作るための土台となります。
次に、自社が戦う市場や競合他社についてリサーチします。
競合はどんな特徴でどんな強み・弱みがあり、価格帯やターゲット顧客層はどうかなどを調査します。
調査の結果を踏まえて、市場での自社の立ち位置(ポジショニング)を明確にします。
次は「誰に」届けるかを具体化するために、顧客リサーチとペルソナ設定を行います。
既存顧客へのアンケートやインタビュー、SNS上の口コミ、レビューサイトなどを調査し、ターゲットとなる顧客が抱える具体的な悩み、欲求、価値観を深く掘り下げます。
そして、リサーチで得た情報をもとに、商品を届けたい理想の顧客像である「ペルソナ」を、一人の人物のように詳細に設定します。
ペルソナとは、年齢、性別、職業、年収、価値観やライフスタイル、抱えている悩みに至るまで、まるで実在する一人の人物のように詳細に設定したものです。
ペルソナを設定することで、「誰に語りかけるのか」が明確になり、メッセージの解像度が格段に上がります。
ペルソナ設定、最初は「なんだか面倒だな…」と感じるかもしれません。
でも、たった一人に向けて書くだけで、不思議なことに文章がとても具体的で、感情に響くものに変わります。
ペルソナを設定したら、その特定の人物に向けて、伝えるべき提供価値(ベネフィット)を発見します。
ステップ1で分析した商品の特徴と、ステップ2の競合分析の結果を掛け合わせ、
「このペルソナが持つ悩みを、競合ではなく自社の商品だからこそ、どのように解決できるのか」を考え抜きます。
ここで見つけたベネフィットこそが、セールスコピー全体の核となります。
バリスタ厳選の特別なオーガニック豆が毎月届く。
だから、さやかさんは慌ただしい朝の時間を『自分のための上質なリラックスタイム』に変えることができる。
最高の香りに包まれて一日を始めれば、心に余裕が生まれ、仕事の創造性も高まる。
ペルソナと提供すべきベネフィットが明確になったら、いよいよ執筆です。
しかし、いきなり書き始めるのではなく、まずは文章の設計図となる「構成案」を作成します。
構成案では、「何を」「どの順番で」伝えるかを決めます。
この後の章で詳しく解説する「型(フレームワーク)」を活用すると、説得力のある流れをスムーズに作ることが可能です。
構成案という骨格がしっかりしていれば、執筆中に話が逸れたり、伝えたいことがぶれたりするのを防げます。
設計図が完成したら、それに沿ってペルソナに語りかけるように、心を込めて文章を書いていきましょう。
生成AIを活用した文章構成案作成プロンプト
文章構成の壁打ちに生成AIに何パターンか構成案を出してもらうのも高い品質のセールスコピーを書くのに役立ちます。
下記プロンプトでは、製品・サービス情報、市場・競合情報、ペルソナ情報、ベネフィット、目的を入力することで構成案を提案してくれます。
# 命令書
あなたは、数々のヒット商品を生み出してきたプロのセールスライターです。以下の前提条件と制約条件に基づいて、ターゲットの心に深く響くセールスコピーの構成案を3パターン作成してください。
# 前提条件
## 1. 製品・サービス情報
- **製品名**: {ここに製品名を入力}
- **特徴**: {ステップ1で分析した特徴を入力}
- **強み**: {ステップ1で分析した強みを入力}
## 2. 市場・競合情報
- **競合**: {ステップ2で分析した競合の特徴などを入力}
- **自社の立ち位置**: {ステップ2で分析した自社の立ち位置を入力}
## 3. ペルソナ情報
{ステップ3で分析したペルソナの情報を入力}
## 4. 提供するベネフィット
- {ステップ4で発見した、ペルソナに提供する最も重要なベネフィットを入力}
## 5. アウトプット
- **出力媒体**: {ランディングページ、メールマガジンなど、媒体を指定}
- **フレームワーク**: {PASONAの法則、CREMAの法則など、使用したい型を指定}
- **トーン&マナー**: {例: 親しみやすく、専門家として信頼できるトーン。読者を励ますような、ポジティブなトーン。など}
# 実行
上記のすべての情報を統合し、指定されたフレームワークと出力媒体に最適化された形で、ペルソナが「これはまさに私のための商品だ」と感じるようなセールスコピーを作成してください。特に、ペルソナの悩みに寄り添い、ベネフィットを感情に訴えかける形で表現することを重視してください。
# 制約条件
- 誇大広告と見なされる表現(「絶対に」「100%」など)は使用しないでください。
- 文体は、ペルソナのような方が、まるで自分に語りかけられているかのように感じる、パーソナルで共感的なトーンを維持してください。ただし、特定の個人名(「〇〇様」など)は使用せず、同じ悩みや価値観を持つターゲット層全体に届くような、Webサイトやランディングページで用いる一般的な呼びかけ(例:「〜と感じていませんか?」「〜なあなたへ」など)を使用してください。
- 専門用語は避け、中学生でも理解できるような平易な言葉を使用してください。
# 命令書
あなたは、数々のヒット商品を生み出してきたプロのセールスライターです。以下の前提条件と制約条件に基づいて、ターゲットの心に深く響くセールスコピーの構成案を3パターン作成してください。
# 前提条件
## 1. 製品・サービス情報
- 製品名: オーガニックコーヒー豆の月額制サブスクリプションサービス「Morning Ritual」
- 特徴: 希少なシングルオリジン豆、焙煎したてを直送、バリスタが毎月厳選。
- 強み: スーパーでは手に入らない高品質・高鮮度な豆と、その豆が持つストーリー。
## 2. 市場・競合情報
- 競合:
- 大手メーカー: 手頃だが、豆の鮮度や個性は追求しにくい。
- 大手カフェチェーン: 店舗での体験が主であり、自宅での最高の体験とは異なる。
- 小規模ロースター: 高品質だが、店舗に行く手間と、初心者には敷居の高さがある。
- 自社の立ち位置: スーパーの手軽さと専門店のこだわりを両立し、自宅での最高のコーヒー体験を提供する。「毎朝のコーヒーを、自分を整える『儀式』へと高める」というコンセプトと鮮度で差別化。
## 3. ペルソナ情報
- 名前: 鈴木 さやか
- 年齢: 38歳
- 職業: フリーランスのグラフィックデザイナー
- 年収: 600万円
- ライフスタイル: 夫と二人暮らし。仕事とプライベートのバランスを重視し、安さよりも質を求める。丁寧な暮らしに憧れており、朝のコーヒータイムを重要な儀式と捉えている。
- 抱えている悩み: 在宅ワークでオンオフの切り替えが難しい。毎日のコーヒーがマンネリ気味で、スーパーの豆では満足できなくなってきた。専門店へ行く時間もない。
## 4. 提供するベネフィット
- バリスタ厳選の特別なオーガニック豆が毎月届く。だから、さやかさんは慌ただしい朝の時間を「自分のための上質なリラックスタイム」に変えることができる。最高の香りに包まれて一日を始めれば、心に余裕が生まれ、仕事の創造性も高まる。
## 5. アウトプット
- 出力媒体: ランディングページ
- フレームワーク: PASBECONAの法則
- トーン&マナー: 丁寧で、ライフスタイルを提案するような、上質で信頼できるトーン。
# 実行
上記のすべての情報を統合し、指定されたフレームワークと出力媒体に最適化された形で、ペルソナが「これはまさに私のための商品だ」と感じるようなセールスコピーを作成してください。特に、ペルソナの悩みに寄り添い、ベネフィットを感情に訴えかける形で表現することを重視してください。
# 制約条件
- 誇大広告と見なされる表現(「絶対に」「100%」など)は使用しないでください。
- 文体は、ペルソナのような方が、まるで自分に語りかけられているかのように感じる、パーソナルで共感的なトーンを維持してください。ただし、特定の個人名(「〇〇様」など)は使用せず、同じ悩みや価値観を持つターゲット層全体に届くような、Webサイトやランディングページで用いる一般的な呼びかけ(例:「〜と感じていませんか?」「〜なあなたへ」など)を使用してください。
- 専門用語は避け、中学生でも理解できるような平易な言葉を使用してください。
【コンセプト】理想と現実のギャップに共感し、毎朝の小さな変化がライフスタイル全体を豊かにすることを伝える。
キャッチコピー:
「いつからだろう、朝が『こなすもの』になったのは。」
丁寧な暮らしに憧れはあるけれど、現実は、鳴り響くアラーム、慌ただしく淹れるいつものコーヒー、そしてすぐにPCの電源を入れる毎日。
仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちな在宅ワークで、心から「新しい一日が始まった」と感じられる瞬間を、失っていませんか?
慌ただしい朝、時間に追われて淹れた一杯のコーヒー。
本当はもっと香りや味わいを楽しみたいのに、いつの間にか「ただ眠気を覚ますため」の作業になっている…。
そんな毎日に、ふと寂しさや物足りなさを感じること、ありますよね。その気持ち、とてもよくわかります。
だから私たちは、毎朝のコーヒーを 「自分を取り戻すための、上質な儀式」に変えるご提案をします。
オーガニックコーヒーのサブスクリプション「Morning Ritual」は、ただのコーヒー豆をお届けするのではありません。
世界中から厳選された、ストーリーを持つ一杯と共に、あなただけの静かで満たされた朝の時間をお届けします。
封を開けた瞬間に広がる、焙煎したての芳醇なアロマが、部屋の空気を一変させます。
お湯を注ぐと、豆がふっくらと膨らむ様子は、まるで呼吸をしているかのよう。
その一杯をゆっくりと味わう5分間が、慌ただしいだけの「朝の時間」を、思考と心を整える「自分だけの儀式」へと変えてくれるのです。
心に生まれた小さな余白が、午前中の仕事に新しいひらめきをもたらし、一日を穏やかな気持ちで過ごすための土台となるでしょう。
【お客様の声】「この香りに包まれたくて、自然と早起きになりました(30代・女性デザイナー)」「毎月届く豆のストーリーを読むのが楽しみ。世界が広がります(40代・フリーランス)」
【バリスタのこだわり】 私たちが信頼する〇〇氏のプロフィールと、豆選びの哲学を紹介。
【品質の証明】 JAS認証オーガニック豆のみを使用していることを明記。
毎月あなたに届く、特別な体験
私たちの3つの約束
自分だけの『朝の儀式』を、特別な価格で
通常価格 4,500円/月(税込・送料込)
【初回限定】特別なウェルカムオファー
3,200円(税込・送料込)
いつでも解約・スキップは可能です。まずはお気軽にお試しください。
希少な豆のため、毎月お届けできる数には限りがございます。
今月お届けする〇〇(国名)の豆は、今回を逃すと次回の入荷は未定です。
この特別な出会いを、あなたの朝のために。
↓ ボタン ↓
**「私だけの特別な朝を始める(初回28%OFF)」
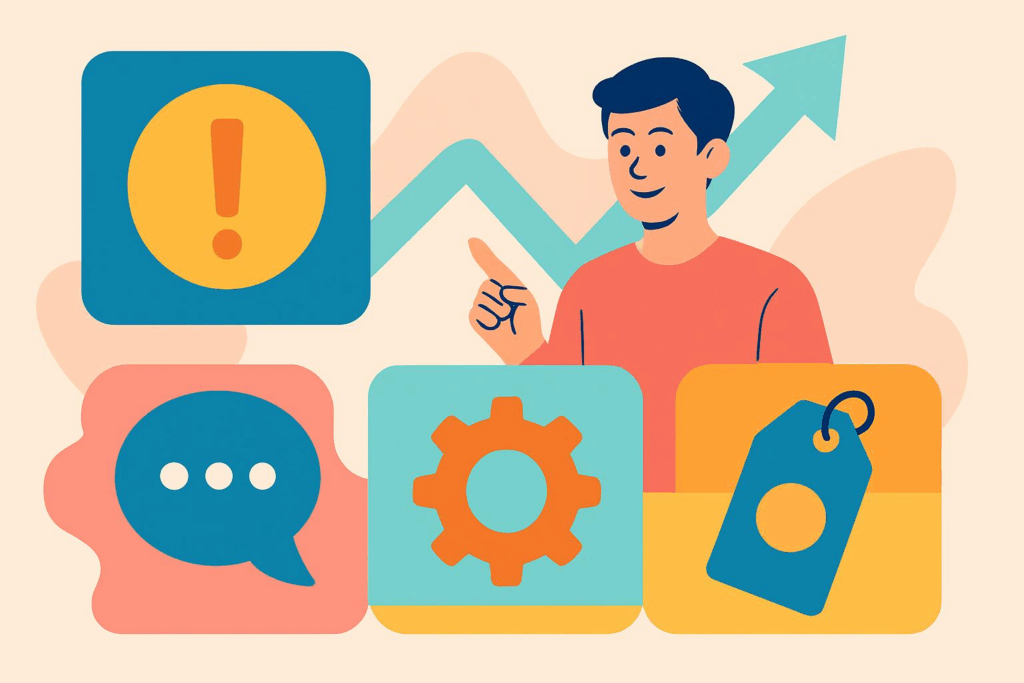
セールスライティングには、成果を出しやすい文章構成の「型(フレームワーク)」が数多く存在します。
型を活用すれば、再現性高く、読者の心を動かし、行動を促す文章を書けるようになります。
ここでは、代表的な型を特徴別ごとに、それぞれの構成要素と書き方のポイントを解説します。
まずは、あなたが「これなら使えそう」と感じたものを1つ選んでみてください。
個人的には、汎用性が高い「新PASONAの法則」から試してみるのをおすすめします。
日本の著名なマーケターである神田昌典氏が提唱した、非常に強力で有名なフレームワークです。
読者が抱える問題を指摘し、解決策を提示することで行動を促します。
当初は「PASONAの法則」として発表されましたが、より読者に寄り添う形に改良された「新PASONAの法則」が現在では主流となっています。
| 構成要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| Problem 問題提起 | 読者が抱えている悩みや問題を具体的に提示します。 |
| Agitation 煽り | 問題の深刻さや、放置した場合のリスクを伝え、危機感を煽ります。 |
| Solution 解決策 | 問題の具体的な解決策として、商品やサービスを提示します。 |
| Narrow down 絞り込み | 「期間限定」「人数限定」など、今すぐ行動すべき理由を伝えます。 |
| Action 行動喚起 | 購入や申し込みなど、具体的な行動を促します。 |
新PASONAの法則では、2番目の「Agitation(煽り)」が「Affinity(親近感・共感)」に置き換えられています。
これにより、売り込み感を和らげ、読者に共感しながら解決策を提案する、より丁寧なアプローチが可能になります。
| 構成要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| Problem 問題提起 | 読者が抱えている悩みや問題を具体的に提示します。 |
| Affinity 親近感・共感 | 「私もそうでした」のように、読者の悩みに寄り添い、共感を示します。 |
| Solution 解決策 | 問題の具体的な解決策として、商品やサービスを提示します。 |
| Offer 提案 | 価格、特典、保証など、具体的な取引条件を魅力的に伝えます。 |
| Narrow down 絞り込み | 「期間限定」「人数限定」など、今すぐ行動すべき理由を伝えます。 |
| Action 行動喚起 | 購入や申し込みなど、具体的な行動を促します。 |
現代の消費者は一方的な売り込みに敏感なので、恐怖を煽るのではなく「その気持ち、わかりますよ」と隣に座って寄り添う姿勢が、何よりの信頼につながります。
PASBECONA(パスビーコーナ)の法則は、神田昌典氏が新PASONAの法則をさらに発展させたフレームワークです。
証拠や具体的な内容を加えることで、論理的な説得力を高めています。
高額な商品やBtoB向けのサービスなど、読者が慎重に購入を検討する場面で特に有効です。
| 構成要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| Problem 問題提起 | 読者が抱える問題を明確にします。 |
| Affinity 親近感・共感 | 読者の状況に共感し、信頼関係を築きます。 |
| Solution 解決策 | 問題に対する解決策を提示します。 |
| Benefit 利得 | 解決策によって得られる未来の利益(ベネフィット)を伝えます。 |
| Evidence 証拠 | お客様の声や専門家の推薦、実績データなど客観的な証拠を示します。 |
| Contents 内容 | 提供する商品・サービスの具体的な内容を分かりやすく説明します。 |
| Offer 提案 | 価格、特典、保証などの取引条件を魅力的に伝えます。 |
| Narrow down 絞り込み | 緊急性や希少性を訴え、行動を後押しします。 |
| Action 行動喚起 | 具体的な行動とその方法を分かりやすく示します。 |
PASBECONA(パスビーコーナ)の法則は、情報量が多くなるので、LP(ランディングページ)のような縦長のページと相性が良いと思います。
QUESTフォーミュラは、アメリカの著名なコピーライターであるマイケル・フォーティン氏が提唱した型です。
特徴は「Educate(教育)」のステップにあり、読者に解決策の価値を理解・納得してもらいながら、自然な流れで購入へと導きます。
まだ問題意識が低い潜在顧客へのアプローチにも適しています。
| 構成要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| Qualify 絞り込み | 「こんなことでお悩みではありませんか?」と呼びかけ、ターゲットを明確にします。 |
| Understand 理解・共感 | 読者の悩みや痛みを理解し、共感を示して信頼関係を築きます。 |
| Educate 教育 | 問題の原因や解決策の重要性を伝え、商品がなぜ有効なのかを教育します。 |
| Stimulate 興奮・刺激 | 商品を手に入れた後の素晴らしい未来を見せ、購買意欲を刺激します。 |
| Transition 変化・行動喚起 | 購入という行動へスムーズに移行させます。 |
CREMA(クレマ)の法則は、最初に「Conclusion(結論)」を提示するのが最大の特徴です。
忙しい読者や、すでに情報収集を進めている読者に対して、要点を素早く伝えたい場合に効果的です。
論理的な構成で、説得力のある文章を書きやすくなります。
| 構成要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| Conclusion 結論 | 文章全体で最も伝えたい結論や提案を最初に述べます。 |
| Reason 理由 | その結論に至った理由を説明します。 |
| Evidence 証拠 | 理由を裏付ける客観的なデータや具体例を示します。 |
| Method 手段 | 結論を実現するための具体的な方法として、商品やサービスを提示します。 |
| Action 行動喚起 | 読者に取ってほしい行動を具体的に促します。 |
BEAF(ビーフ)の法則は、製品やサービスの紹介に特化したフレームワークです。
最初に顧客にとっての「Benefit(利益)」を伝えることで、読者の関心を強く引きつけます。
Webサイトの商品紹介ページや、レビュー記事などに応用しやすい型です。
| 構成要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| Benefit 利益 | 商品を使うことで顧客が得られる利益や、実現できる理想の未来を伝えます。 |
| Evidence 証拠 | その利益が得られる根拠や、利用者の声などを示します。 |
| Advantage 競合優位性 | 競合他社の製品と比べて優れている点をアピールします。 |
| Feature 特徴 | 製品の機能やスペック、価格などの具体的な特徴を説明します。 |
伝説のコピーライターであるロバート・コリアーが提唱した、物語の流れを汲んだ文章構成です。
読者の感情に訴えかけ、自然な流れで読み進めてもらうことを重視しています。
この型を意識するだけで、文章に説得力と引き込む力が生まれます。
| 構成要素 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 書き出し | 読者の好奇心を刺激し、「もっと読みたい」と思わせます。 |
| 描写や説明 | 提案の全体像を描写し、その魅力を伝えます。 |
| 動機や理由付け | 提案がなぜ読者の役に立つのかを具体的に説明します。 |
| 保障や証明 | 証拠や保証を提示し、読者の不安を取り除きます。 |
| 決め手の一言や 不利益 | 行動しないことのデメリットを伝え、決断を促します。 |
| 結び | 読者が次に取るべき行動を明確に示します。 |
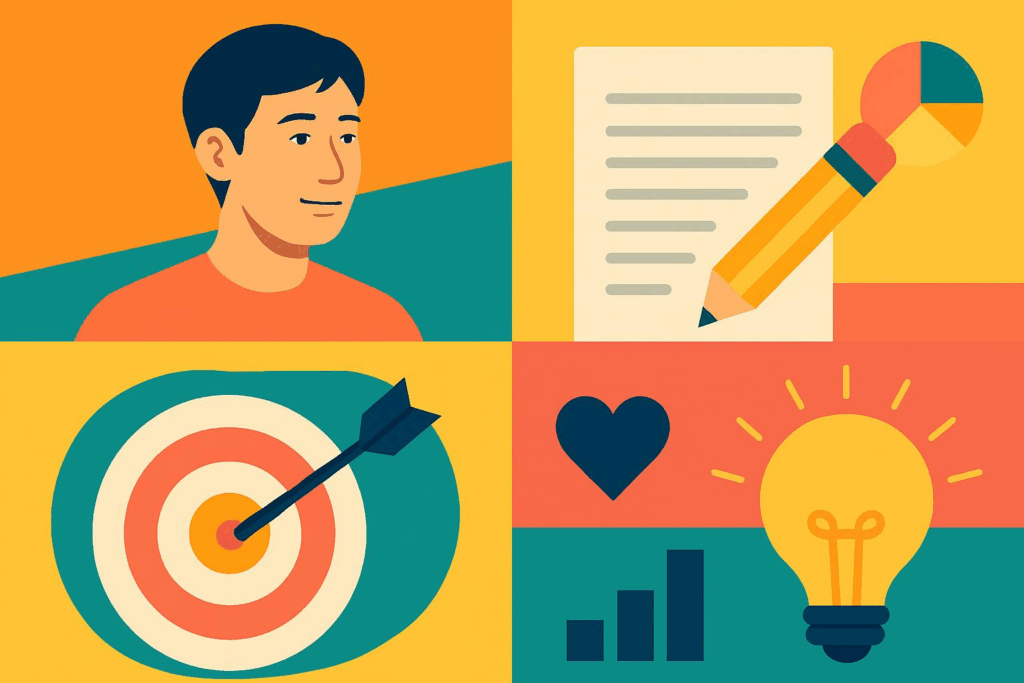
セールスライティングの型を理解したら、次はその効果を最大限に引き出すための実践的なコツを学びましょう。
文章は「キャッチコピー」「導入文」「本文」「締め」の4つのパーツに分けられます。
それぞれのシーンで読者の心を動かすためのポイントを解説します。
キャッチコピーやタイトルは、読者が最初に目にする最も重要な部分です。
ここで興味を引けなければ、本文を読んでもらうことはできません。
読者が思わずクリックしたくなるような、魅力的なタイトル作りのコツを紹介します。
本文をどれだけ魂を込めて書いても、タイトルでクリックされなければ、その記事は存在しないのと同じになってしまいます。
優れたキャッチコピーを作るためのフレームワークとして「4U原則」があります。
これは、以下の4つの要素を盛り込むことで、コピーの訴求力を高める手法です。
すべてを含める必要はありませんが、意識することでタイトルの質が格段に向上します。
タイトルに具体的な数字や権威性のある情報を加えることで、信頼性と説得力が増します。
例えば、「たくさんの人が満足」と書くよりも「顧客満足度98%」と数字で示す方が、具体性が高く、信頼されやすくなります。
「専門家が推薦」や「業界No.1の実績」といった権威性は、読者に安心感を与え、選択を後押しする効果があります。
BTRNUTSS(バターナッツ)は、神田氏が代表を務めるアルマ・クリエイション株式会社が提唱しているメソッドです。
前項と被る部分もあるのですが、様々な視点で見出しが作れますのでご紹介します。
| Benefit 有益性 | 読者にとってのメリットや価値が明確に伝わるか |
|---|---|
| Trust 信頼性 | 権威や証拠などで信頼感を与えるか |
| Rush 緊急性 | 今すぐ行動しなければならないと感じさせるか |
| Number 数字 | 数字や統計などで具体性や説得力を高めるか |
| Unique 独自性 | 他とは違う特徴や差別化を示すか |
| Trendy 話題性 | 時事や流行などに関連づけるか |
| Surprise 意外性 | 予想外や驚きの情報を提供するか |
| Story 物語性 | 物語やエピソードなどで興味や感情を引き出すか |
上記の8つの要素を盛り込むことで、効果的なタイトルや見出しを作り上げることができるとしています。
導入文は、タイトルで惹きつけた読者の関心をさらに高め、本文へとスムーズに誘導する役割を担います。
ここで読者が「自分に関係ない」と感じてしまうと、すぐに離脱されてしまいます。
まずは「こんなお悩みはありませんか?」と読者が抱えているであろう問題を具体的に提示します。
そして「その気持ち、よくわかります」と共感を示すことで、読者は「この記事は自分のためのものだ」と感じ、親近感を抱きます。
この共感が、書き手への信頼の第一歩となります。
ここでの目的は「この記事は、あなたのためのものですよ!」と伝えることです。
読者は常に自分にしか興味がありません。最初の数行で心をつかめるかどうか、最初の勝負どころです。
製品の「特徴(Feature)」をただ羅列するのではなく、その特徴が顧客にとってどのような「便益(Benefit)」をもたらすのかを伝えましょう。
例えば、「軽量設計」という特徴は、「持ち運びが楽で、外出先でも気軽に使えます」という便益に繋がります。
顧客は製品そのものではなく、製品がもたらす良い変化にお金を払うのです。
商品やサービスを利用した結果、読者の未来がどのように明るく変わるのかを具体的に想像させましょう。
「このツールを使えば、面倒な作業から解放され、家族と過ごす時間が増えます」のように、理想の未来を提示することで、購買意欲を強く刺激できます。
本文では、導入文で高めた読者の期待に応え、商品やサービスへの理解と信頼を深めていきます。
論理と感情の両面に訴えかけることが重要です。
人は単なるデータや事実よりも、物語に心を動かされます。
商品開発の裏話や、ある顧客が悩みを克服して成功したエピソードなどを語ることで、読者は感情移入し、商品への興味を深めます。
物語は記憶に残りやすく、ブランドへの愛着を育む効果もあります。
人は理屈で納得し、感情で行動するので、
ストーリーテリングは、セールスライティング最強の武器の一つだと私は思っています。
自社製品の優位性を客観的に示すために、競合との比較データを活用するのは有効な手段です。
価格、機能、サポート体制などを表形式で分かりやすく示すことで、読者は合理的に判断しやすくなります。
ただし、他社を不当に貶めるような表現は避け、誠実な情報提供を心がけましょう。
主張の信頼性を高めるために、客観的な証拠(エビデンス)を提示します。
これには、第三者機関による調査データ、専門家の推薦コメント、メディア掲載実績などが含まれます。
また、「お客様の声」や「導入事例」は、社会的証明(ソーシャルプルーフ)として機能し、「他の人も使っているなら安心だ」という心理を働かせ、読者の不安を解消します。
クロージングは、読者の背中をそっと押し、具体的な行動へと導くための最終段階です。
ここでの訴求が成約率を大きく左右します。
単に価格を提示するだけでなく、オファー(提案)全体を魅力的に見せることが大切です。
「今だけの特別価格」「豪華特典付き」「安心の全額返金保証」などを組み合わせることで、価格以上の価値を感じさせ、お得感を演出できます。
魅力的なオファーは、お客様が行動する最後のひと押しをしてくれます。
人は何かを得る喜びよりも、失うことの痛みを強く感じる傾向があります(損失回避の法則)。
この商品やサービスを利用しなかった場合に「現状の悩みが解決しない」「ライバルに差をつけられてしまう」といった未来のリスクを提示することで、「今すぐ行動しなければ」という気持ちを喚起します。
読者が次にとるべき行動を、明確かつ具体的に示しましょう。
「今すぐお申し込みはこちら」「まずは無料で資料請求」のように、分かりやすい言葉で行動を促します(CTA:Call to Action)。
ボタンの色を目立たせたり、申し込みフォームへのリンクを分かりやすく配置したりすることも重要です。
「手続きが面倒そう」「失敗したらどうしよう」といった読者の心理的な障壁を取り除きましょう。
「お申し込みはたったの3分」「30日間全額返金保証付き」のように、行動へのハードルを下げる一言を添えることで、読者は安心して一歩を踏み出しやすくなります。
不安を先回りして取り除いてあげる。「大丈夫ですよ」とそっと背中を押してあげるような、優しい一言が成約率を大きく変えることがあります。
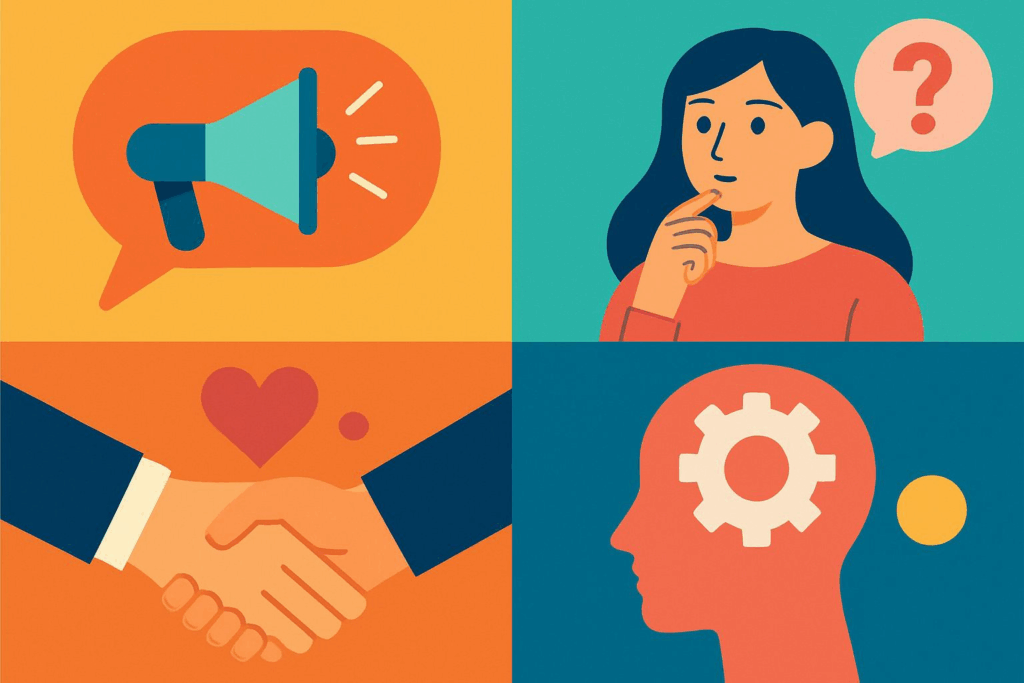
セールスライティングの効果をさらに高めるには、人の心理を理解し、文章に活かすことが大切です。
ここでは、読者の心を動かし、行動を後押しする代表的な心理効果を、目的別に分かりやすく解説します。
これらのテクニックを使えば、売り込まずに信頼を得ながら、自然と成果につなげられます。
心理学テクニックは非常に効果的ですが、忘れてはいけないのは「誠実さ」と「信頼関係を構築しよう」という姿勢です。
人は情報を得て判断する際に、特定の心理的な偏りの影響を受けやすいものです。
この仕組みを理解することで、商品やサービスの価値をより効果的に伝えられます。
アンカリング効果とは、最初に提示された情報(アンカー)が、その後の意思決定に大きな影響を与える心理現象です。価格交渉や商品の値付けでよく利用されます。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 最初に見た数字や情報が基準となり、後の判断がそれに引っ張られる。 | 「通常価格10,000円 →特別価格7,000円」のように、通常価格を先に見せることで、割引後の価格がよりお得に感じられます。 |
松竹梅の法則(ゴルディロックス効果)は、3つの選択肢が提示された場合、多くの人が無意識に真ん中の選択肢を選んでしまう心理効果を指します。極端な選択を避けたいという心理が働くためです。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 3段階の選択肢があると、多くの人が真ん中を選びやすい。 | 料金プランを「基本プラン」「おすすめプラン」「プレミアムプラン」の3つ用意し、最も販売したいプランを真ん中に配置することで、選ばれやすくなります。 |
バーナム効果とは、誰にでも当てはまるような曖昧で一般的な記述を、まるで自分のことを的確に言い当てているかのように感じてしまう心理現象です。占いや性格診断などでよく使われます。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 多くの人に共通する事柄を、自分だけに当てはまることだと錯覚する。 | 導入文で「Webからの集客が思うようにいかず、悩んでいませんか?」と問いかけることで、読者は「自分のことだ」と感じ、文章に強く引き込まれます。 |
商品を購入してもらうには、まず読者からの信頼を得ることが不可欠です。ここでは、文章の説得力を高め、読者との信頼関係を築くための心理効果を紹介します。
権威性の法則は、専門家や社会的地位の高い人、組織など、権威のある存在の意見や推薦を信じやすくなる心理効果です。専門的な知識がない分野ほど、この効果は強くなります。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 専門家や権威のある人の意見は、正しいと感じやすい。 | 「〇〇大学教授 推薦」「導入実績No.1」「有名雑誌掲載」といった情報を提示することで、商品やサービスの信頼性が一気に高まります。 |
正直なところ、自分で「この商品はすごいです!」と100回言うよりも、専門家の一言の方がずっと説得力があると思います。
バンドワゴン効果とは、多くの人が支持しているものに対して、さらに多くの支持が集まる現象です。「みんなが使っているなら安心だ」という心理が働き、判断を後押しします。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 多くの人が選んでいるものに、魅力を感じて同調したくなる。 | 「利用者数10万人突破」「お客様満足度95%」といった具体的な数字を示すことで、読者に安心感を与え、購買意欲を高めることができます。 |
両面提示は、良い面(メリット)だけでなく、悪い面(デメリット)も正直に伝えることで、かえって信頼性を高める手法です。誠実な姿勢が伝わり、売り込み感を和らげる効果があります。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| メリットとデメリットの両方を伝えることで、誠実さが伝わり信頼されやすくなる。 | 「高性能ですが、使いこなすには少し慣れが必要です」のように、あえて弱みを見せることで、正直な企業であるという印象を与え、信頼関係を築けます。 |
読者の注意を引きつけ、最後まで読んでもらい、そして行動に移してもらうためのテクニックです。少しの工夫で、読者の反応は大きく変わります。
ツァイガルニク効果は、人は完成されたものよりも、未完成なものや中断されたものの方が気になって記憶に残りやすい、という心理現象です。テレビ番組の「続きはCMの後で」が代表例です。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 物事が未完了であると、緊張感が保たれ、記憶に残りやすくなる。 | タイトルや導入文で「売上が伸びない本当の理由とは?」のように問いを投げかけ、答えを本文で明かす構成にすると、読者は続きが気になり読み進めてくれます。 |
イエスセットの法則は、相手が「はい(イエス)」と答えやすい簡単な質問を繰り返すことで、本題の要求(本当に同意してほしい提案)にも同意してもらいやすくする交渉術です。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 小さな「イエス」を積み重ねることで、大きな「イエス」を引き出しやすくなる。 | 「もっと時間を有効活用したいですか?」「安定した売上を確保したいと思いませんか?」といった質問を重ねた後に、商品の提案をすることで、スムーズに受け入れられやすくなります。 |
損失回避の法則とは、人は「利益を得る喜び」よりも「損失を避けること」を優先する傾向があるという心理です。「得をしたい」という気持ちよりも「損をしたくない」という気持ちの方が、人の行動に強く影響します。
| 概要 | セールスライティングでの活用例 |
|---|---|
| 何かを得るよりも、何かを失うことに強い苦痛を感じる。 | 「本日限定価格」「先着50名様のみ」「この機会を逃すと1万円損します」といった限定性や緊急性をアピールすることで、「今行動しないと損をする」という心理が働き、購入を強く後押しします。 |

優れた型やコツを駆使しても、読者の信頼を損なう表現や法律に触れる内容があれば、成果につながるどころか、企業の信用問題に発展しかねません。
ここでは、セールスライティングで避けるべきNG例と、必ず押さえておきたい注意点を解説します。
読者との信頼関係は、セールスライティングの基盤です。何気なく使った言葉が、読者に不信感や警戒心を抱かせてしまうことがあります。ここでは、特に注意したいNG表現をまとめました。
| NG表現の例 | 問題点と改善のポイント |
|---|---|
| 「絶対に」「100%」「必ず」 | 効果を保証する断定的な表現は、誇大広告と見なされる可能性があります。客観的なデータや実績を示し、「〇〇の可能性があります」「多くの方が〇〇と実感しています」のように、事実に基づいた表現にしましょう。 |
| 根拠のない「業界No.1」「日本初」 | 第三者機関による調査データなどの明確な根拠がない限り、最上級表現の使用は避けるべきです。もし根拠がある場合は、「※〇〇調べ(調査期間:2024年1月~3月)」のように、出典を明記することが不可欠です。 |
| 「これを逃すと一生後悔します」 | 読者の不安を過度に煽る表現は、不快感を与え、信頼を失う原因になります。恐怖心ではなく、商品やサービスがもたらすポジティブな未来や、得られるベネフィットを中心に訴求しましょう。 |
| 専門用語や業界用語の多用 | 読者が内容を理解できなければ、当然ながら行動にはつながりません。専門的な内容を伝える場合でも、中学生にも分かるような平易な言葉で説明したり、具体例を挙げたりする工夫が必要です。 |
文章の構成一つで、読者の購買意欲は大きく変わります。たとえ一つひとつの文章が魅力的でも、全体の流れが悪いと読者は途中で離脱してしまいます。成約を遠ざけてしまうNGな構成を理解し、読者をスムーズに行動まで導きましょう。
| NGな構成 | 問題点と改善のポイント |
|---|---|
| 冒頭から商品 を売り込む | 読者はまず自身の悩みを解決したいと考えています。いきなり商品を売り込まれると、広告だと判断してすぐにページを閉じてしまいます。まずは問題提起や共感を示し、読者の悩みに寄り添う姿勢を見せることが大切です。 |
| 特徴の羅列で 終わっている | 商品のスペックや機能(特徴)だけを伝えても、読者は「だから、自分にどういいの?」と感じてしまいます。その特徴によって読者がどのような素晴らしい未来(ベネフィット)を手に入れられるのかを、具体的に描写しましょう。 |
| 行動喚起 (CTA)が 不明確 | 記事を最後まで読んでも、次に何をすれば良いか分からなければ、読者は行動できません。「今すぐ無料で試す」「詳しい資料をダウンロードする」のように、取ってほしい行動を明確に示し、申し込みボタンなどを分かりやすく設置しましょう。 |
セールスライティングを行う上で、法律の遵守は絶対条件です。特に広告表現に関しては、「景品表示法(景表法)」が大きく関わってきます。知らなかったでは済まされないため、基本的な知識を身につけておきましょう。
景品表示法では、主に以下の2つの不当表示が禁止されています。
この他にも、健康食品や化粧品を扱う場合は「薬機法(旧薬事法)」、通信販売を行う場合は「特定商取引法」など、関連する法律は多岐にわたります。意図せず法律に違反してしまう事態を避けるためにも、表現には細心の注意を払いましょう。
詳しくは、消費者庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認することをおすすめします。

最後にセールスライティングに取り組む際に参考になる本を三冊ご紹介します。
まずご紹介するのは、本記事でも紹介したロバート・コリアー氏の著書「伝説のコピーライティング実践バイブル―史上最も売れる言葉を生み出した男の成功事例269」です。
ロバート・コリアー氏の実体験に基づいた事例を豊富に紹介しながら、セールスライティングの考え方やノウハウ、型などを紹介しています。
700ページを超える大冊ではありますが、セールスライティングに取り組む際は必ず読んでおきたい一冊と言えるでしょう。
続いてご紹介するのは、セールスライターである寺本隆裕氏の著書「ウェブセールスライティング習得ハンドブック」です。
先に紹介した「伝説のコピーライティング」と異なり事例こそ少なめですが、顧客の心理やセールスコピーの書き方、コツなどを詳しく解説している良書です。
この一冊を読めば、セールスライティングに関する基本的なノウハウは網羅できるため、ぜひご一読ください。
最後にご紹介するのは、行動経済学の第一人者の一人であるダン・アリエリー氏の著書「予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」」です。
セールスライティングとは直接関連はないものの、セールスライティングに役立つ心理現象を行動経済学の観点から解説しており、とても参考になります。
アリエリー氏の巧みな筆致により行動経済学の前提知識がなくとも、楽しみながら読み進めることができるでしょう。
この記事では、売れる文章を書くためのセールスライティングの型とコツを解説しました。
成果を出すのに特別な才能は必要ありません。PASONAの法則などの「型」を使えば、初心者の方でも論理的で説得力のある構成を簡単に作れます。
さらに心理学に基づいた「コツ」を実践することで、読者の心を動かし、自然と行動を促せます。
まずは一つの型を選んで、とにかく書き始めることから始めてみてください。
実践を重ねることで、あなたの言葉は着実に成果を生み出します。