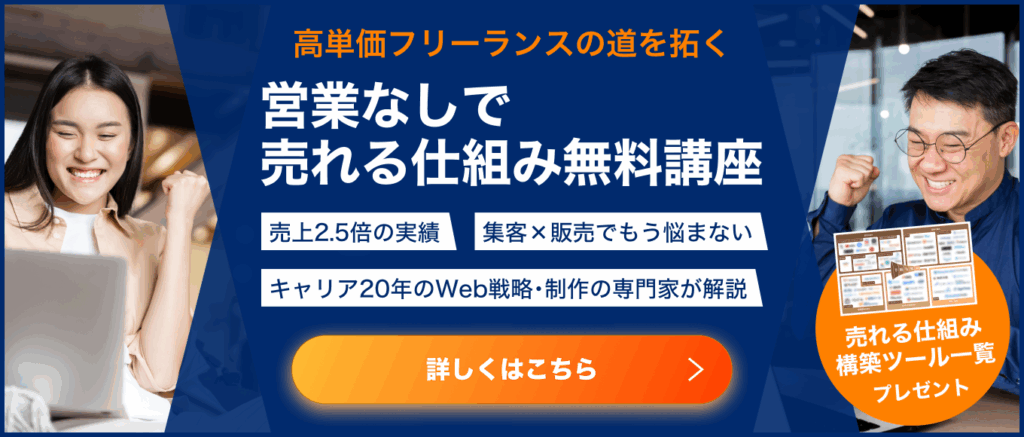


この記事は上記のような思いをお持ちの方に向けて、上位表示されるSEO記事の条件や制作の流れを踏まえつつ、書き方やポイントをわかりやすく解説します。
SEO記事制作に役立つツールもご紹介していますので、ぜひ最後までご確認ください。

まずは上位表示されるSEO記事の主な条件を確認していきましょう。
一つ目の条件は検索意図を踏まえた内容の記事にするという点です。
SEO記事ではキーワードの検索意図、つまり「どういったニーズや悩みを解決しようと思ってユーザーは検索したのか」という点を分析し、その意図に沿った情報を提供しなければなりません。
日本における検索エンジンのシェアはGoogleとYahoo!が大半を占めますが、Yahoo!はGoogleの検索エンジンを採用しているため、実質SEOの対象となるのはGoogleとなります。
Googleの検索エンジンはユーザーを重視しており、ユーザーの検索意図に合ったコンテンツを上位表示させる仕組みとなっているのです。
そのため検索意図を分析し、それに応えられる情報を記事として提供することで、上位表示に繋げることができるのです。
続いて挙げられる条件は独自性とE-E-A-Tが担保されているという点です。
SEO記事に取り組んでいる企業やサービス提供者は多く、大抵の場合ターゲットとした検索キーワードにおいて既にSEO記事が存在しています。
そういった競合記事が多い中で上位表示を勝ち取るには、記事に独自性があり、かつE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の要素が担保されていることが重要になるのです。
記事テーマに関する専門的な資格を持っていたり、豊富な実務経験があったりすることを執筆者情報として記載することで、上位表示を狙うことができるでしょう。
取り上げている情報が新しいことも、上位表示を狙う上で重要な要素です。
ユーザーが検索する際、基本的には「そのテーマに関する最新の情報を得たい」と考えているケースが多いと言えます。
そのためSEO記事にはその時点で最新の情報を記載し、情報の鮮度も担保することで、上位表示に繋げられる可能性があるのです。
記事に「いつアップロードしたのか」を記載することで、新しい情報であることをアピールするとよいでしょう。

それでは具体的にSEO記事制作の流れについて、7つのステップに分けて解説します。
まずは戦略策定を行います。
SEO記事制作における戦略策定で決めるべき点は以下の2点です。
ターゲット顧客を決める際は、年齢や性別といった基本的な情報に加えて、価値観や志向、情報収集傾向など、様々な要素を加味したペルソナを策定します。
次にペルソナの各購買検討段階(認知から購買に至るプロセス)におけるニーズや悩み、提供すべき情報の方向性などをまとめたカスタマージャーニーを作成しましょう。
次に対策を行う検索キーワードを選定するステップへと入ります。
まずは策定したペルソナとカスタマージャーニーでまとめた情報を基にしながら、「どういった検索キーワードを使って、ニーズを満たそうとするのか」を考えていきましょう。
候補となる対策キーワードをある程度抽出できた後は、検索ボリューム(検索数/月)や競合記事の品質などを踏まえながら、実際に記事化していくキーワードを絞り、優先順位を付けていきます。
検索ボリュームの大きなビッグワードと呼ばれるキーワードは、基本的に競合記事も質が高いものが多く、その分上位表示の難易度が上がる点は注意しましょう。
対策キーワードの選定ができた後は、競合記事の調査と検索意図の把握に取り組みます。
上位表示されているということは、検索エンジンから検索意図を満たしていると評価されている証拠でもあります。
そのため記事化するキーワードを使って検索を実施し、上位表示されている記事の内容を調査することで、検索意図を掴むことができるのです。
最低でも上位5記事、できれば10記事程度のタイトルや見出し、取り上げている情報などをチェックし、記事で取り上げるべき情報に目星を付けていきましょう。
続いて構成案の作成に入ります。
SEO記事を制作する際はいきなり執筆に入らず、競合記事の調査結果と検索意図を踏まえて、記事の骨子、つまりタイトルと見出しをまず作成するのです。
構成を作成する際はターゲットとするキーワードに加えて、関連するキーワードも調査した上で、見出しなどに取り入れていくことで、上位表示できる可能性を高めることができます。
「どこに何が書いてあるのかをユーザーにわかりやすく伝える」という前提は守りながら、適切にキーワードを配置していくことがポイントです。
SEO記事が上位表示できるかは、ほとんど構成で決まると言っても過言ではないため、しっかりと作り込んでいきましょう。
次のステップはいよいよ記事の執筆です。
構成案のタイトルや見出しを基に、インターネットなどで情報を収集し、執筆していきます。
ターゲットの視点で、よりわかりやすい表現や言葉はないかを試行錯誤しながら、執筆と推敲を重ねていくことになるでしょう。
また構成案はあくまで「案」ですので、執筆過程で不足している情報に気が付く場合もあります。
その際は新たに見出しを加えるなど、柔軟に対応していくことで、記事の品質を高めることができるでしょう。
記事の書き方に関するポイントは、この後ご紹介します。
続いてのステップは記事の校正です。
記事を書き終えた後は、誤字脱字のチェックや論理破綻などがないかを確認しつつ、よりわかりやすくなるように修正していきましょう。
また読み返して「この文章はいらないな」と感じたものは、遠慮なく削っていくことで、記事の要点をより目立たせることが可能です。
なお記事の校正については、初稿を書き終えた日に実施せず、日を改めて行うことをおすすめします。
日を改めることで執筆者の目線から、読者の目線に切り替えてチェックできるので、より精度の高い校正ができるのです。
最後のステップは入稿です。
運営しているブログやWebサイト上にアップロードしましょう。
少なくともタイトルタグ(<Title>記事タイトル</Title>)や見出しタグ(<h1〜3>見出し</h1〜3>)は設定し、検索エンジンに情報が正しく伝わるように入稿することがポイントです。
また入稿の際に目次を設けることで、読者の利便性を高めることができるので、忘れずに対応しましょう。
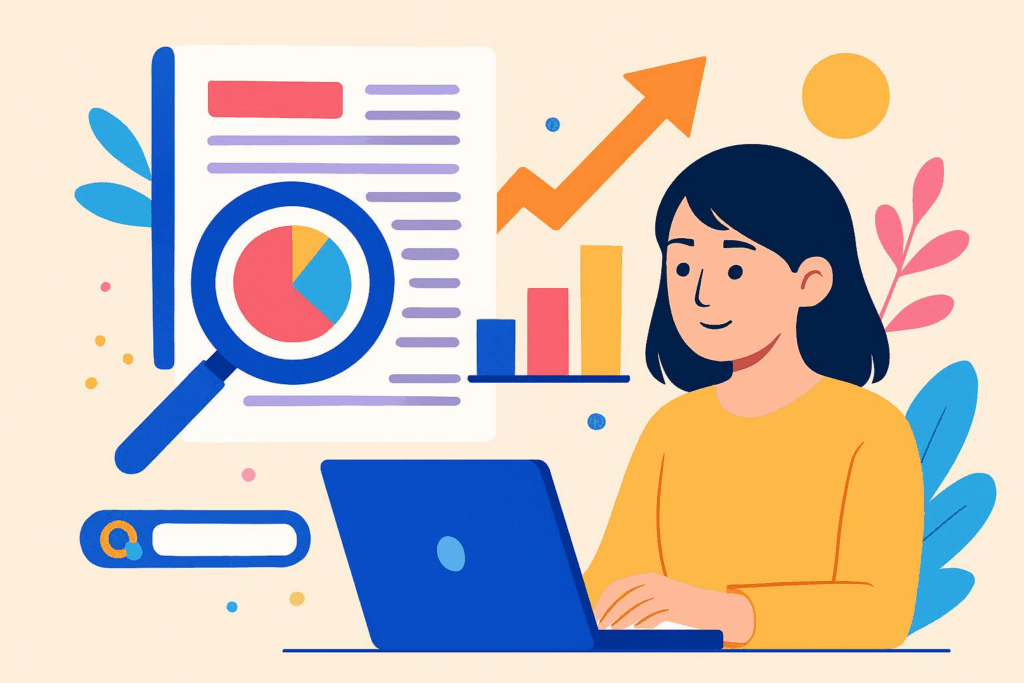
ここからはSEO記事の書き方におけるポイントをご紹介します。
記事を執筆する際は、構成に含まれている各見出しを肉付けするイメージで執筆していきましょう。
白紙の状態から執筆するよりも、「何について書くのか」が明確になっている方が情報収集や執筆が捗ることは言うまでもありません。
だからこそ執筆を始める前に、構成を作り込んでおくことが重要になるのです。
構成を作り込むにはある程度の時間がかかりますが、後々の執筆作業を効率化させるためにも、手間を惜しまないことをおすすめします。
SEO記事を執筆する際は、結論や重要な情報から執筆するPREP法を参考にしましょう。
PREP法とは以下のステップで執筆する手法です。
情報を求めているユーザーは手っ取り早く必要な情報が欲しいと考えているため、長々と前提を解説していると、離脱される可能性が高くなります。
そのため可能な限り結論や重要な情報から書き出し、その後に根拠や例などで補完していくようにしましょう。
執筆する際どこまで専門的な内容を伝えるのかといった点は、読者のリテラシーに合わせる必要があります。
ターゲットとする読者が記事テーマについて、ある程度リテラシーがあると想定される場合は内容を深くし、専門用語なども活用することで、ニーズを深く満たすことができるでしょう。
逆にリテラシーがない読者をターゲットとする場合は、内容も初歩的なものに限定しつつ、専門用語などもできる限り使わない方が無難です。
もしターゲットのリテラシーが分からない場合は、誰が読んでも理解できる内容や言葉で執筆することをおすすめします。
SEO記事に限った話ではありませんが、必要な情報を伝える上で最小限の文字数で執筆することもポイントです。
文字数が多ければ多いほど記事の品質が高くなるわけではなく、扱うテーマによって最適な文字数は異なります。
2000文字程度が妥当なテーマもあれば、10000文字でも不十分なケースもあるのです。
最適な文字数については、一概に「○○文字」と断言できませんが、競合記事を分析する際に、文字数も併せてチェックすることで大よその範疇を把握できるでしょう。
外部サイトの情報を記事内で引用する際は、必ず参照元を記載してください。
SEO記事を書くにあたって、テーマによっては他記事の内容を引用したり、公的機関が発行しているレポートを引用したりするケースもあります。
これらを引用する際に、引用であることを伏せて記事に取り入れてしまうと、著作権の観点で法律に触れてしまう恐れがあるのです。
そのため引用している旨をわかりやすい位置に記載し、参照元のリンクも併せて設置しましょう。
公的機関は引用時のガイドラインを提示しているケースが多いので、もし引用する際はそういったガイドラインがないか調べてみるのも一つです。
SEO記事において数字や固有名詞などを取り上げる際は、必ず一次情報をコピペしてください。
文章をコピペすることはNGですが、数字や固有名詞は手入力するとどうしても誤表記に繋がるリスクが生じてしまいます。
統計データの数字や人物名、製品名といった固有名詞は誤表記してしまうと、誤った情報を伝えることに直結してしまうため、必ずコピペするようにしましょう。
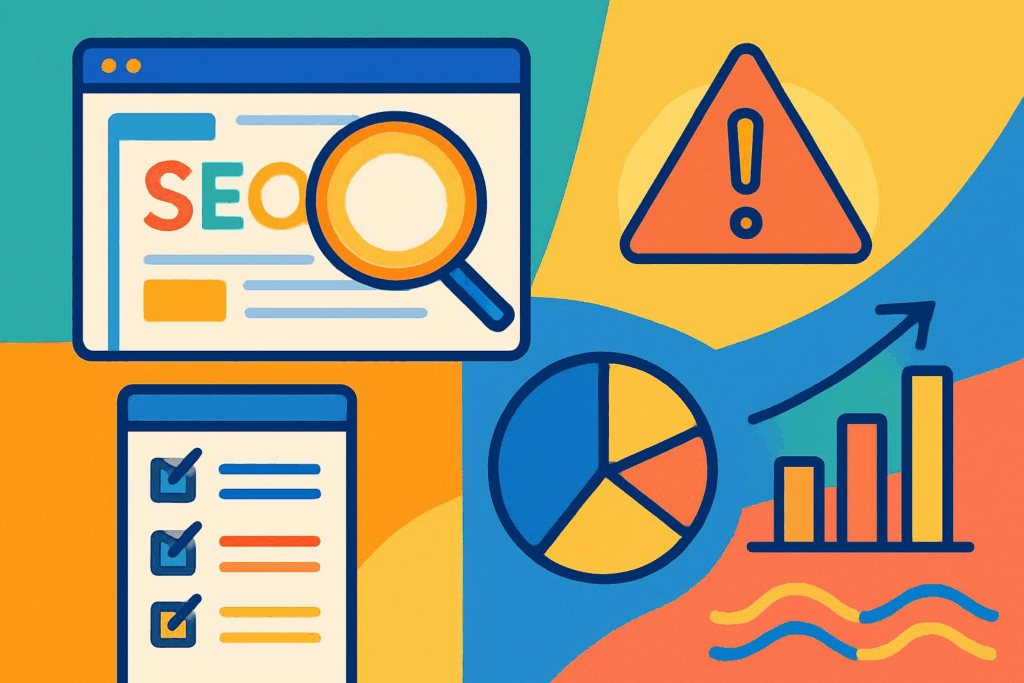
SEO記事の書き方と併せて、制作時の注意点についてご紹介します。
一つ目の注意点は、上位記事を模倣しただけのコンテンツにならないようにするという点です。
構成を作成する際、上位表示されている記事を参考にすることは勿論よいことですが、単純に模倣したような構成では検索エンジンからコピーコンテンツと判断されてしまいます。
コピーコンテンツと判断されてしまうと上位表示されないどころか、ペナルティが課されるといったリスクが生じます。
そのため上位記事の構成は参考にしつつも、独自の観点や項目を取り入れることが重要になるのです。
SEO記事においてキーワードや関連ワードを活用することは重要ですが、不自然に詰め込み過ぎると逆効果になります。
キーワードを使いたいばかりに見出しが不自然になったり、本文が読みにくくなったりすれば、記事としての価値が下がってしまうのです。
そのため、あくまでターゲット読者のニーズを最優先に、構成の見出しや本文を制作しなければなりません。
「SEOという概念がなくても同じことをするか」という観点も踏まえ、キーワードを不自然に詰め込んでいないかを確認していきましょう。
ブログやWebサイトでSEO記事を継続的に提供していく場合、コンテンツの重複には注意が必要です。
関連コンテンツを準備することは重要ですが、ほとんど同じ内容を記載しているような記事が多数存在している場合、記事だけでなくサイト全体の評価が下がってしまうのです。
そのため、これまで執筆してきたSEO記事を適切に管理しつつ、新たにSEO記事を制作する際は過去の記事を参照し、重複を回避できるようにしておきましょう。
SEO記事は定期的にリライトを行い、情報の鮮度を保ちましょう。
執筆時点では最新だった情報でも、その後放置していれば情報が古くなってしまい、検索順位も下がってしまう可能性があります。
そのため定期的に競合記事調査を行いつつ、更新すべき情報があった場合はリライトしていかなければなりません。
情報更新だけでなく、内容の改善も含めたリライトを定期的に実施することで、長期にわたって集客効果を発揮するSEO記事に仕上げることができるでしょう。
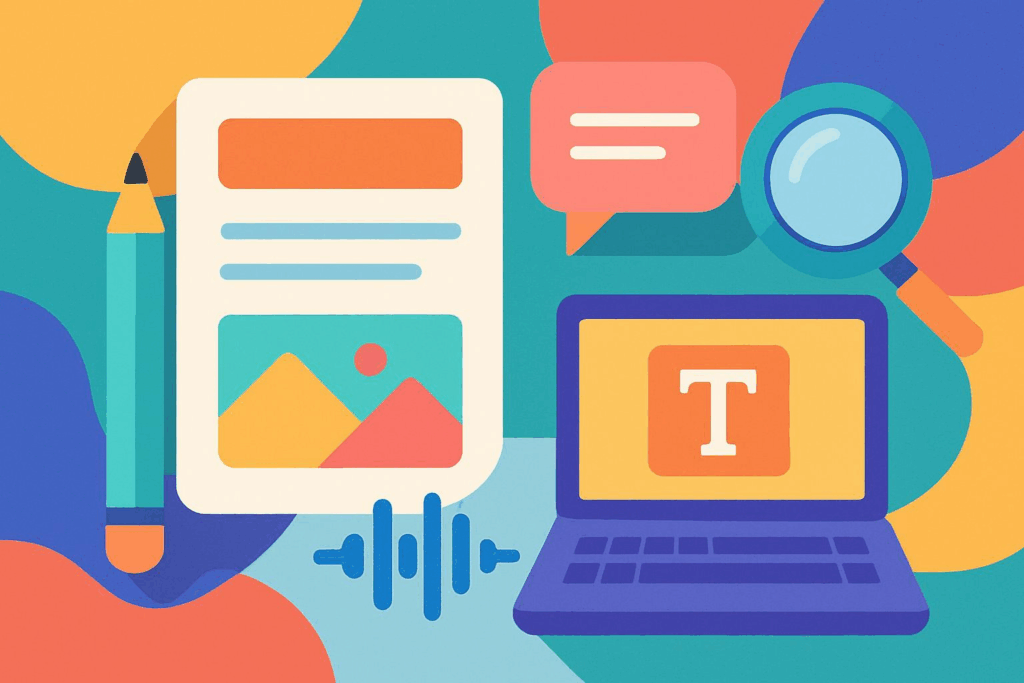
最後にSEO記事制作に役立つツールをご紹介します。
Googleキーワードプランナーは、Google広告の入札キーワードを選定するためのツールで、特定キーワードの検索ボリュームを確認できます。
広告を運用することで詳細な検索ボリュームを把握できますが、広告運用をしなくても、検索ボリュームの概算(100〜1000件/月といった形)は把握可能です。
そのためSEO記事制作におけるキーワード選定に活用できるでしょう。
関連ワードやそれぞれの検索ボリュームも併せてチェックできるので、SEO記事制作において必須ツールと言えます。
MOZはWebサイトのドメインオーソリティ(以下、DA)やページオーソリティ(以下、PA)をチェックできるツールです。
DAとPAは、ドメインとWebページがそれぞれ検索エンジンからどの程度評価されているかを示す指標となっています。
DAやPAの値が高いほど評価が高いといえ、もし競合調査の際に上位サイトのDAやPAが高い傾向にあれば、それだけ上位表示が難しくなるのです。(ちなみに平均的なDA・PAは30~50程度となっています。)
MOZをインストールしてGoogleで検索をかけることで、検索結果表示ページで各WebページのDAやPAをチェックできるため、キーワード選定に役立てることができるでしょう。
PAやDAをチェックするだけであれば無料で活用できますので、ご興味あればご確認ください。
ラッコキーワードは関連キーワードや共起語を自動抽出できるツールです。
Googleのサジェストなどを含めた関連キーワードを取得できるため、構成作成において役立ちます。
また見出し抽出機能もあり、上位20記事分の見出しをCSV形式で取得できるため、競合記事の見出し調査に役立つでしょう。
ただし本文までは抽出できませんので、本文を確認したい場合は直接記事を確かめる必要がある点は注意しましょう。
無料かつ会員登録なしでも利用できますが、回数制限などがあります。
ChatGPTは無料で利用できるAIによるチャットサービスで、「~を教えてください」といった形で質問することで、様々な情報を収集できます。
また単純な質問ではなく、「○○をターゲットとした、○○の記事を作りたい。見出し案を作ってください。」といった形で指示することで、記事の構成案を自動生成できるのです。
文字数や見出しの数なども指定できるため、それなりの構成案を作成できます。
ただし、AIによる自動生成であるため情報が古かったり、見出しがわかりにくかったりすることもあります。
そのため、あくまで参考に留め、自分で作成した構成に抜けている観点がないかを確認する際に活用する形がよいでしょう。
CopyContentDetector®は制作した記事と競合サイト記事との類似性などを確認できるツールです。
無料で利用でき、文章や使っている文字列の一致率などを把握できます。
またCookieを利用して、過去に自分がチェックしたテキストデータも残されるため、自分で執筆した文章間の一致率なども確認可能です。
自分自身で記事を制作する際に、類似コンテンツになっていないかを把握するために使える上、外部ライターを活用する場合もコピぺ防止に活用できるでしょう。
今回はSEO記事の書き方をテーマに、上位表示のための条件や制作の流れなどを解説しました。
質の高いSEO記事を制作できれば、検索エンジンからの集客が安定し、見込み顧客の獲得に効率よく繋げることができます。
定期的なリライト作業は必要ですが、広告のように費用をかけることなく、中長期にわたって集客効果を発揮するため、費用対効果にも優れた手法と言えるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、SEO記事制作に取り組んでみてください。