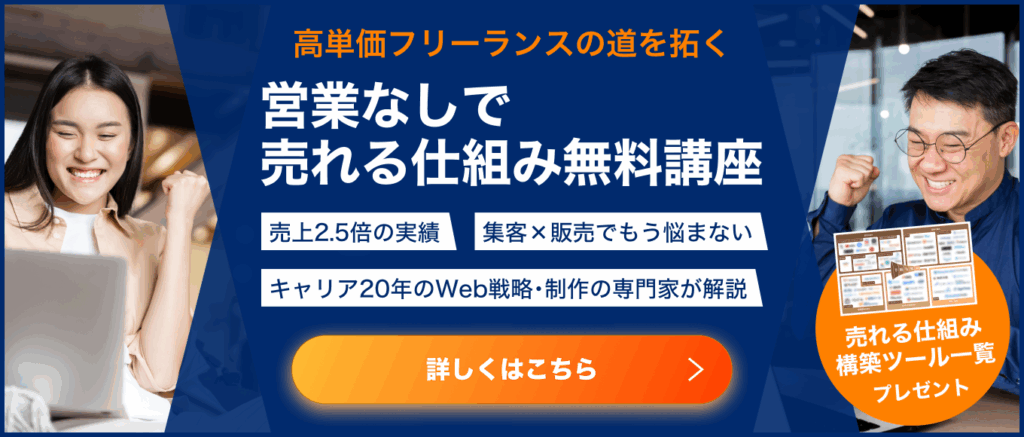

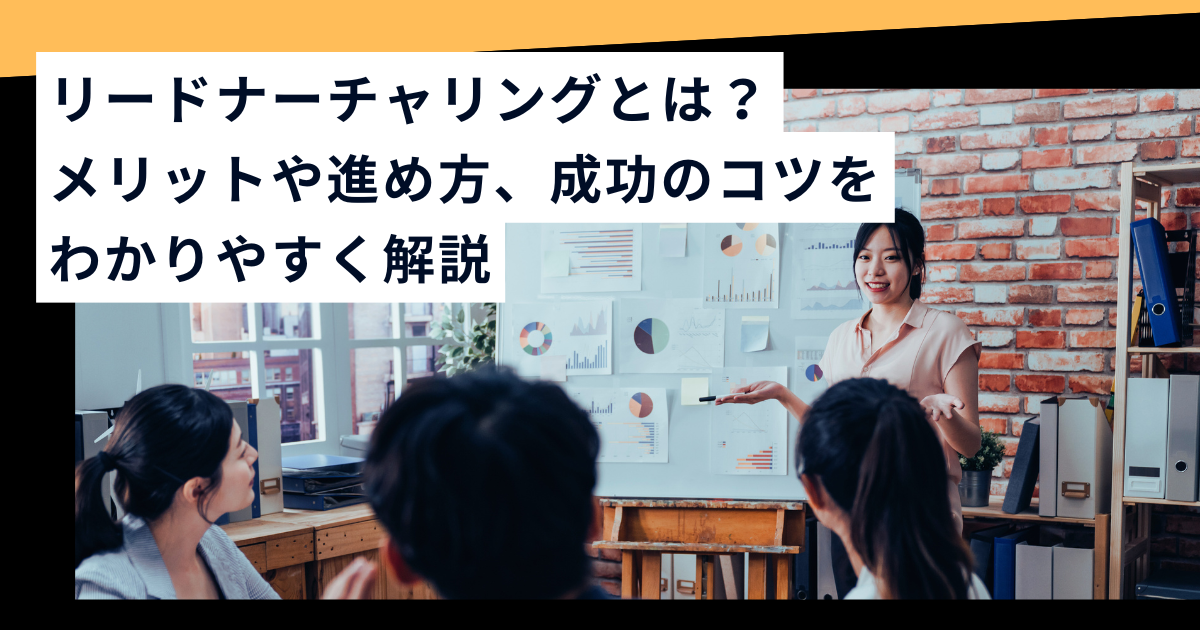
この記事は、リードナーチャリングの概要や進め方、手法などをまとめて解説していきます。
他にもメリット・デメリット、取り組みを成功させるためのコツについてもご紹介していますので、ぜひ最後までご確認ください。

まずはリードナーチャリングについて、概要や重要とされる理由などについて確認していきましょう。
リードナーチャリングとは、見込み顧客(リード)育成の役割を担うマーケティングプロセスです。
見込み顧客と一口に言っても、人によって購買意欲のレベルは異なります。
コンタクトを取った時点ですでに検討段階にいる見込み顧客もいれば、興味があるだけという見込み顧客もいるでしょう。
そのため見込み顧客それぞれの状態に合わせて、購買意欲を高めていくためのコンテンツ提供やコミュニケーションを図る必要があるのです。
リードナーチャリングが重要な理由として、インターネットの普及による顧客行動の変化やリード獲得方法の多様化が挙げられます。
インターネットの普及により、顧客は自らの興味度に応じて情報収集を能動的に行うようになったため、これらの情報ニーズに対して的確に応える必要性が生じています。
またリード獲得方法も技術の進展に伴い多様化しました。
獲得した方法によって見込み顧客の状態は異なるため、各見込み顧客に合わせたアプローチを実施するリードナーチャリングの重要性も増してきたと言えるでしょう。
リードナーチャリングと関連した概念として、リードジェネレーションがあります。
リードジェネレーションは、マーケティングプロセスにおける見込み顧客獲得プロセスのことを指し、リードナーチャリングの前段階で行われる取り組みとなります。
SEO(検索エンジン最適化)やWeb広告など様々な手法を駆使し、商品・サービスに関心を持つターゲット層の認知を得て、メールアドレスなどの顧客情報を獲得していくのです。
リードジェネレーションについては以下の記事で解説していますので、ぜひ併せてご確認ください。

ここでリードナーチャリングに取り組むメリットとデメリットについて、確認しておきましょう。
リードナーチャリングのメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
リードナーチャリングに取り組むことで、既に保有している見込み顧客資産を最大限活用できます。
休眠顧客や商談途中で失注した顧客に対しても、適切にアプローチすることで顧客化を図ることができるのです。
リードナーチャリングでは、見込み顧客の状態を見極め、各タイミングで必要となる情報やコンテンツを提供していきます。
そのためアプローチが受け入れられやすく、結果として購買などのアクションを促すことができるのです。
リードナーチャリングでは接点を持った見込み顧客に対して、放置するのではなく、継続的にコンタクトを図り、顧客化を目指していきます。
顧客化の可能性が高い見込み顧客を見逃すリスクも少なく、結果として機会損失を防ぐことができるでしょう。
デメリットとしては以下のような点が挙げられます。
リードナーチャリングを行うには、様々なコンテンツを提供していく必要があります。
これらのコンテンツを準備するには、相応の手間や費用といったコストがかかるのです。
またリードナーチャリングに取り組んでも、実際に成果が出るまでには、一定以上の期間がかかります。
見込み顧客の状態によっては、中長期でのコミュニケーションが必要な場合もあるのです。
リードナーチャリングは見込み顧客の育成プロセスであるため、育成対象となる顧客が必要となります。
そのため、そもそも見込み顧客を十分に獲得していなければ、リードナーチャリングは機能しないのです。
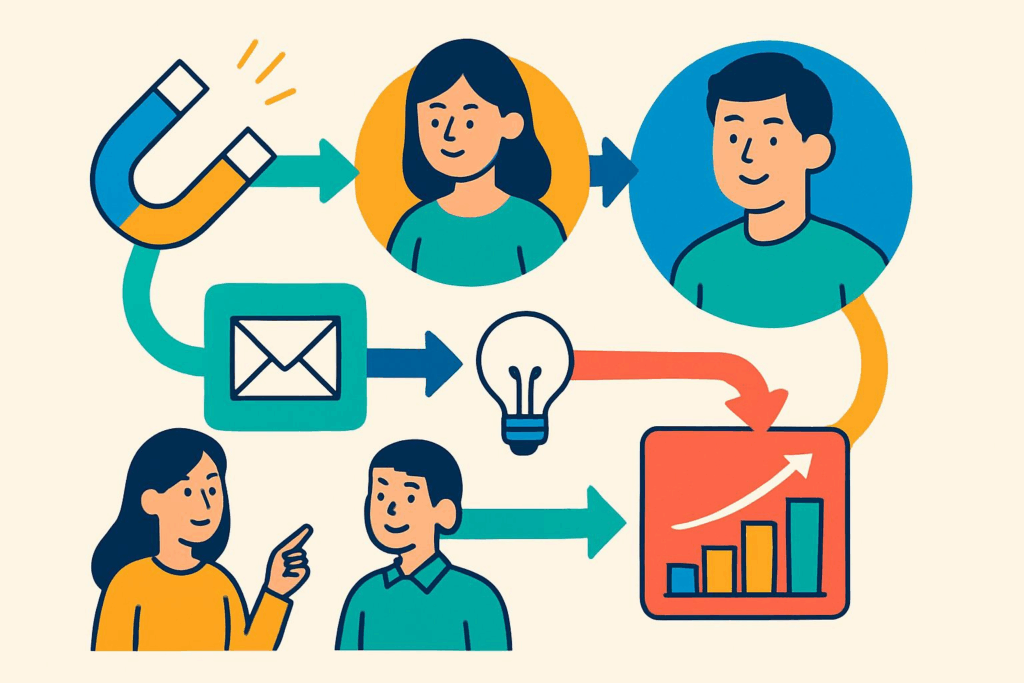
次にリードナーチャリングの進め方について、5つのステップに分けてご紹介します。
リードナーチャリングの最初のステップは、リード情報の集約です。
これまで獲得してきた見込み顧客に関する情報を、顧客管理ツールなどに集約していきます。
マーケティングオートメーションやCRMといったツールが理想ですが、GoogleスプレッドシートやExcelなど、顧客に関する情報を適切に管理できるツールであれば問題ありません。
休眠顧客や失注顧客に関する情報も忘れずに集約していきましょう。
次のステップはリードの分類です。
一つ目のステップで集約した見込み顧客を、様々な属性を基にいくつかのセグメントに分類していきましょう。
BtoBであれば売上規模や業種、事務所の所在地や窓口担当者の役職といった属性を基に、分類することが可能です。
BtoCの場合は年齢や性別、居住地や家族構成、利用しているSNSやデバイスなどを基に分類しましょう。
続いて、先のステップで分類したセグメントの中から、ターゲットとするセグメントを決めます。
さらにターゲットセグメントを基に、具体的な人物像であるペルソナを策定しましょう。
ペルソナを策定する際は、セグメントに含まれる属性に肉付けしていくイメージで、様々な要素を加えながら詳細化します。
ペルソナを策定した後は、ペルソナの各購買段階におけるニーズや悩み、提供すべき情報などをまとめたカスタマージャーニーを策定し、見込み顧客を分析しましょう。
カスタマージャーニーで整理したペルソナのニーズや思考などを起点に、どのようなコンテンツやコミュニケーションを実施すれば購買意欲を高められるのかを検討しましょう。
コンテンツや施策同士の繋がりも意識し、認知から購買・契約に至るルートを確立していくイメージで、検討することがポイントになります。
コンテンツ制作については内製で行う他、外注するという選択肢もあるため、リソースと相談しながら、効率的に進めていきましょう。
最後は施策実施と効果検証のステップへと入ります。
制作したコンテンツやコミュニケーション施策を実際に展開し、効果を検証していくことになるでしょう。
効果検証の結果、課題や問題が見つかれば改善していく必要もあります。
このように効果検証と改善のPDCAサイクルを回していくことで、より精度の高いアプローチが実現できるのです。
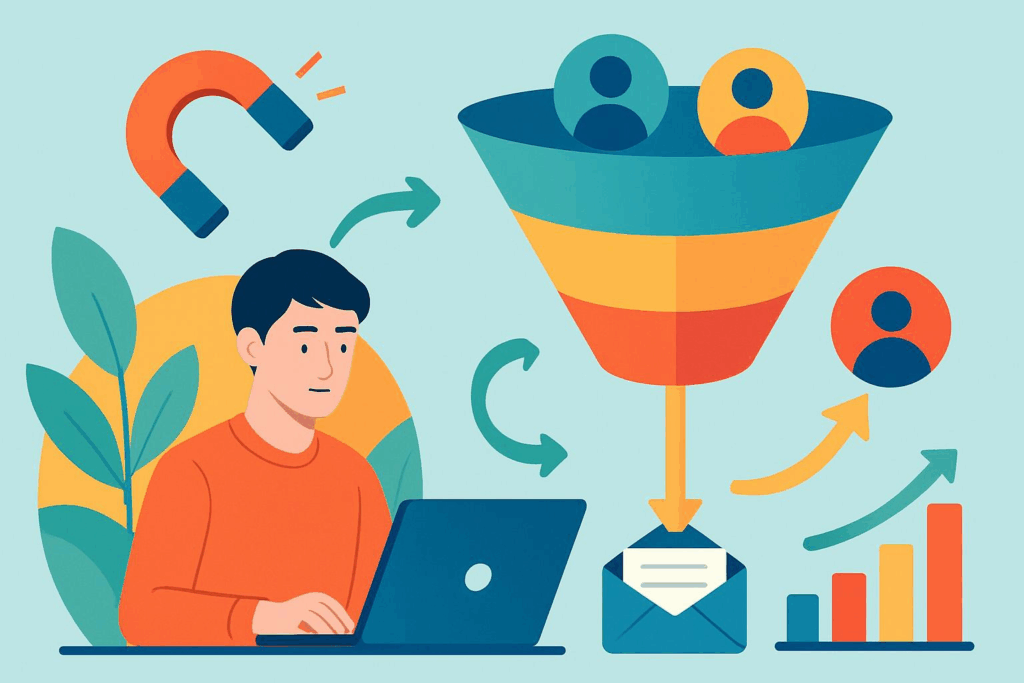
ここからはリードナーチャリングに用いられる主な手法をご紹介します。
各購買段階における見込み顧客の悩みや疑問を解決するための情報を、ブログ記事として提供します。
ブログ記事はリードジェネレーションにおいて主力となる手法ですが、取り上げる課題やテーマによって、リードナーチャリングにも活用できる優れた手法です。
またブログ記事にSEOを施しておくことで、リードナーチャリング向けのブログ記事でも、新たな見込み顧客を獲得できる可能性があります。
このようにブログ運用は汎用性が高いため、積極的に活用すべき手法と言えるでしょう。
FacebookやX(旧Twitter)、LINEをはじめとするSNSを活用し、見込み顧客との相互的なコミュニケーションを図ります。
役立つ情報を配信するといった活用方法以外に、見込み顧客の投稿をチェックし、必要に応じて投稿などへのリアクションを行うといった活用方法もあります。
他にも新しいブログ記事をSNS上で投稿したり、SNS広告を利用したりと、リードナーチャリングにおける幅広い用途に活用できるでしょう。
見込み顧客にとって価値ある情報やサービス紹介などを含めたメールを定期的に配信し、購買意欲を高めていきます。
メール配信には主に、メールマガジンとステップメールの2つの活用方法があります。
情報提供や告知などを中心とするメールマガジンと、商品・サービスの宣伝を段階的に行うステップメールを適切に使い分けることで、効果的に見込み顧客の購買意欲を高めることができるでしょう。
リターゲティング広告は、Webサイトに一度訪れた見込み顧客に対して表示できるWeb広告です。
購買検討を一旦ストップしている見込み顧客に対して、製品・サービスを想起してもらうことができ、Webサイトへの再訪問などを促すことができます。
ただし、リターゲティング広告が表示されることに対して、ネガティブな印象を抱く見込み顧客も一定数いることが考えられるため、その点は留意しておきましょう。
見込み顧客に対して、定期的にフォローのためのコンタクトを図り、接点を維持しつつ、購買意欲を高めていきます。
フォローコンタクトを行う際は状況を確認するだけでなく、見込み顧客の悩みなどをあらかじめ想定しておき、有益な情報を提供するといった取り組みがポイントになるでしょう。
対面でも構いませんが、Web会議システムやLINE公式アカウントなどを用いてコンタクトを行うことで、効率的なフォローコンタクトを実現できます。

最後にリードナーチャリングを成功させるためのコツを確認しましょう。
リードナーチャリングは、見込み顧客に対する理解をどこまで深められるかによって、成否が分かれます。
顧客理解を徹底して深めることで、どのようなタイミングでコンタクトを取るべきか、どういった情報が必要かなどを検討する際に、精度が高まるのです。
そのためペルソナやカスタマージャーニーの策定は勿論、施策やコミュニケーションの効果検証を重ねながら、顧客に対する理解をしっかりと深めていきましょう。
リードナーチャリングの精度を高めていくには、効果検証と改善のサイクルを回していく必要があると述べましたが、そのためには適切なKPI・指標を設定しなければなりません。
リードナーチャリングにおける主なKPIとしては、以下のようなものが挙げられます。
これらの指標は、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを活用することで簡単にチェックできるので、リードナーチャリングに取り組む際はあらかじめ導入しておくとよいでしょう。
リードナーチャリングの取り組みでは、ブログやメールといった様々なコンテンツを活用することになります。
これらのコンテンツ管理や配信を支援するツールを活用することで、効率的にリードナーチャリングを進めることができるでしょう。
例えばブログ記事を管理するためのCMS(コンテンツマネジメントシステム)や、メール配信システムといったツールは、積極的に活用することをおすすめします。
今回はリードナーチャリングをテーマに、概要やメリット、進め方などをまとめて解説しました。
競合サービスが溢れている状況において、せっかく獲得した見込み顧客を放置していては、機会損失に繋がりかねません。
そのためリードナーチャリングに取り組み、見込み顧客と継続的な接点を維持しながら、購買意欲を高めていくことは欠かせないと言えるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、リードナーチャリングに取り組んでいただければ幸いです。